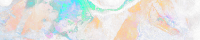 だって君をみてるから
だって君をみてるから
爆豪勝己は羽角のプロである。と言えば表情が乏しくテンションも基本一定なので常にぼうっとしているように見えるしその時どういう感情、状態であるかが分かりづらいのだ。爆豪がそれを難なく読み取れるのは幼少期にめちゃくちゃを観察したというのともずっと隣にいた爆豪に一番気を許していて表情が緩むというのが大きい。昔から、稀に体調を崩すに気付けるのは親か爆豪だけだった。
「羽角どこ行くん?」
「………そと」
「いつもの日向ぼっこ?いってらー」
C組の生徒に見送られ寮の外に出たは何も考えずにぶらぶらと辺りを歩き回る。休日、天気が良い昼間は大抵外でのんびりしているのでクラスメイトも慣れた様子だ。日当たりのいい場所を見つけて木に登り人一人余裕で支えられる太い枝に腰かけ幹に身体を預ける。そよ風が頬を撫で小さく髪を揺らす感覚が心地良い。そうだ、あの日も今日みたいに少し気怠かったな、と中学生の頃のことを思い出しながら目を閉じる。
当時から日々のトレーニングを怠らなかった爆豪。それでもその合間にとの時間も作っていて、トレーニング終わりや休日の空いた時間にの家に行ったり自宅に呼んだりしていた。爆豪にとってとの時間はシンプルに彼に必要なものであったし、自ら行動を起こしたり自身のことを発信してこない彼女の現状確認は幼き頃からの己の役目だと思っているのだ。はと言えば、こちらも今と変わらず休日は日向ぼっこにでかけたり自室でのんびり過ごしていて、この時も家の近くの公園にある樹の枝で休んでいた。なんだか少し身体が重い気がして、ぼんやりと風に揺れる木々の音を聞いていたに声がかかる。
「オイ」
「………勝己」
「何しとんだ」
「……ひなたぼっこ」
「それは見りゃ分かる」
おりてこい、と言葉なく手を動かすのでしばし見つめ合い、彼の隣に下り立つと額に手を当てられた。
「ほらみろ、熱あんだろ」
「……ないと思う」
「あるわ 帰ンぞ」
腕を取られ家まで送り届けられ両親不在だったため一度リビングのソファに座るように促されたは大人しく従う。勝手知ったるなんとやらで体温計を出してきた爆豪から受け取り計ってみると38℃と表示されていた。
「これでよく無いって言えたなァチャンよォ」
「あった」
「ったく……部屋で寝てろ」
「うん………勝己はもう帰る、」
「まだいる、先部屋行ってろ」
その言葉に頷いて自室に戻りベッドに入り少しして。部屋に入ってきた爆豪がベッドの横にあるサイドボードに水を置いて、冷えピタをの額に貼る。
「昨日の課外活動の疲れでたんか」
「……たぶん」
「病院は」
「………だいじょうぶ」
「病院嫌いが……熱続くなら連れてくからな」
幼い頃からが体調を崩すときは大抵、普段と違うことをしたときや人の多いところに行ったことによる心因性のものであることを把握している爆豪は今回もそうであると判断した。は一人でのんびりしているとき以外では家族と爆豪(とその家族)といるときしかリラックスできない。爆豪と同じく幼馴染である緑谷にもだいぶ心を許しているが、それ以外の人間と関わる時間が長い程人疲れしてしまうのだ。その事実がいつも爆豪の心に言い知れぬ感覚を覚えさせる。
「……まだ、いる?」
「あ?ンだよ 寂しーんか」
それはないだろうと思いながら冗談交じりに口角を上げて言えば、ゆっくり繰り返される瞬き。仰向けだった身体をこちら向きに動かして掛け布団の端から手が出てきた。
「ん……にぎってて」
その言葉に一瞬思考が鈍り、の顔と手を順に見つめる。それからベッドに肘をついて手のひらに顎を乗せ、反対の手で出された己のよりも小さなそれを軽く握った。
「晩飯はどーする」
「……とりにく食べたい」
「はっ、胃は元気そうで何よりなこった」
「うん」
「起きるまで待っててやるから寝ろ」
「……ふふ」
小さく笑って目を閉じるに爆豪も目を細める。昔、お泊り保育の時もこうして手を握って寝た。あの時は寝付けなかった自分にが手を伸ばしてくれたのだ。寂しいから握ってくれと。そう言っていたけど、あれは周りの子供の泣き声やいつもと違う環境に落ち着かなかった己を気遣ったのだと思う。元々不思議な存在だが嫌ではなかったし何故か放っておけなかったが、特別であると自覚した日だ。そしてにとっても自分が特別であるという自信がある。さて起きるまで、晩御飯を食べる頃には目を覚ますだろうがそれまで数時間どうしたものか。この穏やかな寝顔なら別に、いつまでも見ていられるのだが。そうして気付けば爆豪も寝入っていた。
「………おはよう」
「…体調は」
「もう大丈夫」
はっと目を開けるとの方が先に起きていたようで視線がかち合う。体温を計ってみると一応微熱にまでは下がっていた。とりあえず栄養取って今晩ゆっくり寝れば明日にはもっと回復しているだろう。の両親は遅くなるようなので爆豪がご飯を用意しついでに自分も一緒に食べる。
「……光己ちゃんには」
「お前探す前に言ってきてる」
「ん」
ちゃんと全部食べ終わるのを見届け、片付けた後。そろそろ帰ると玄関に向かう爆豪の後ろをついてくるに「ちゃんと風呂に入って寝ろ」と伝えながら靴を履いた。それに頷く返事と続けて名前を呼ばれたので振り返る。
「…今日はありがとう」
自分には分かる、薄く微笑んでるの表情に鼻を鳴らしてそのふわふわの髪をポンポンと撫でた。いつもなら外で別れるが出てこなくていいと言われたので閉まるドアに消えていく背中を見送る。何故か昔から彼は分かりにくいはずの自分の変化に気付くんだよな、と不思議に思いながら言われた通りお風呂で温まってゆっくり眠りについた。
穏やかに流れる時に身を任せいつの間にか寝入っていたの意識がスマホの通知音で浮上する。懐かしい夢を見た。ふと思い出したことがそのまま夢に出たようだ。通知を確認すると爆豪から何処にいるのかとメッセージがきており、現在地を送り返す。すると近くにいたのかすぐにやって来た。
「何しとんだ」
「……ひなたぼっこ」
おりてこい、と言葉なく手で合図される。夢と同じだ、と小さく笑いながら彼の隣に下り立つと笑っていることに首を傾げながら額に手を当てられる。
「熱あンだろ」
「ないと思う……ずび」
「ずび、じゃねェよ」
「行くぞ」と腕を引かれ普通科の寮までの道を歩いた。今は前と違ってお互い違う環境で暮らしているのに。やっぱり何故か彼は自分の変化に気付くのだ。