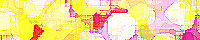 意識
意識
朝日を浴び、ぼんやりと海を眺めている赤い髪が風に揺れるのを視界の端に感じながらその存在について考える。四皇を倒すという目的の合致により組まれた同盟のもと麦わらの一味とローが共に行動するようになってまだ大した時間は経っていない。手配書やニュースで知りはしていたものの初めて邂逅したのは2年前のシャボンディ諸島でのこと、そして少し前に出港したパンクハザードでの再会からこの数日。たった数日過ごしただけとは思えない内容の濃さは置いておいて。それでも一度会ったら忘れないであろう程にキャラクター性が強い一味であるが、その赤い髪の女は比較的大人しく口数の少ない、この一味にしては珍しいタイプではないかと思う。ニコ屋、ロロノア屋でももう少し話す、とこの船に乗ってからほぼ言葉を交わしていない背中を無意識に見つめていたようでくる、とこちらに振り返った。そういえば2年前もパンクハザードでも、記憶の中の長い髪は三つ編みに結われていたような。
「………何か?」
「……いや、」
別に聞くほど気になったわけではない。しかし彼女のことを考えていたのは事実で、相手が気付くほど視線を送っていたのも、事実だ。無表情に首を傾げると見つめ合うこと数秒。話したくないわけでもない、と結われていない髪のことを見ていたと伝えるとパチパチと瞬き視線を少し落とす。
「……いつも、結ってもらってる」
「……へェ、」
「今朝はまだ…、」
本人は結っていてもいなくても気にしないし、自分で結うのもラクではないので余程邪魔に思わない限りはそのままでいるらしい。ただ基本的には朝に女性陣が声を掛けてくれるのだと。静かに話す声は高くも低くもなく耳馴染みが良い。隣に腰を落ち着かせた彼女は表情こそ変わらないがこちらも話す気がないわけではないようで、問えば答えるし一応話題提供もしてくる。年齢を問えば一つ下だった。子どもだとは思わないが顔立ちか、言動か、もう少し下に離れている印象だったので内心驚く。
「ちゅわあ~ん♡朝ごはんできたよお~ん♡」
の隣にいる自分に気付いた途端ハートになっていた眼を逆三角形に尖らせついでとばかりに名を呼ぶサンジに器用なやつだと呆れていると、ちょうどそばを通りがかったチョッパーに「いっしょに行こうっ」と手を引かれて立ち上がり歩き出すがこちらを振り返るので後ろをついて行く。
「ホラ、おにぎり」
「梅干しは入ってねェだろうな」
「あァん!?ちゃんの分しか入れてねェよ」
「俺の真心こもったおにぎりが好きだって♡クソ可愛い顔で言うんだよなあ♡」とだらしない顔でくねくねとその場を去るサンジをスルーして、もぐもぐとすでにおにぎりを頬張っているに目をやった。何だか小動物を見ているような気持ちになる。おにぎり好きなのか。そうか。
それからなんとなく。麦わらの船に乗っている間気付けばの方を見ていることが多かった。ルフィ、ウソップと騒いでいたり。厳密には騒いでいるのは二人だが。ゾロと鍛錬していたり女性陣に世話を焼かれていたり、チョッパーやサンジと話していたり。フランキーにも世話を焼かれているしブルックの演奏を近くで聴いていたり。一味には珍しいタイプだと思ったが当然ながら誰とも自然に過ごしていた。そしてどうにも年齢関係なく世話を焼かれがちなようだ。自分のようにが気になる性分の者が多いらしい。いや違う。別に、気になってるわけじゃないが。ただなんとなく、似ても似つかないが妹を思い出すような。そうでもないような。彼女のことを考えるとすっきりしない、けれど不思議と嫌な気にはならないしそばにいるのは、悪くない。
「……トラファルガーさん」
トラファルガーさん。ここの奴らは人を勝手にトラ男だなんだと呼ぶが、トラファルガーさんだなんて呼び方もそうない。むず痒くなる感覚に、もっとラクに呼べばいいとつい零すと数回の瞬きの後、赤い目が少し細められる。
「…うん ローさん」
「サンジに飲み物もらってきた」と紅茶を手渡され反射的に受け取り、そのままルフィに呼ばれてそちらへ行く背中を見送った。今、もしかして。笑ったのか。笑顔というには程遠かったけれど、確かに眦が下がったような。
「かわいいでしょう?彼女」
紅茶を啜ったところで飛んできた言葉にブ、と思わず咽る。何を、と横を見ればこの一味の中では比較的よく話す部類のロビンがにこやかに立っていた。曰く、読み取れるようになるまで時間がかかるがよく見れば表情に変化があるし、の方も慣れると分かりやすくなるのだと。しっかりしてるようでどこか抜けているというか。自分のことに頓着がない様子が危なっかしくて気になるのだと。聞いてもいないのに教えられる。でも確かにこの短い付き合いでもそれは伺えた。
「フフ、でも彼女は…ルフィが離さないわねきっと」
もちろん彼女だけに限ったことじゃないけれど。そう微笑んで去って行くロビンにそういうのではないと舌打ちをするが、そもそもそういうのではないって何だと自分に問いかける。余計なことを言われたおかげで必要以上にのことを考えてしまうようになった。紅茶を味わいながらルフィと話している姿を眺め変わらず無表情だなと思っていたその瞬間。ルフィの言葉にふわり、と破顔するが目に映る。時が、止まったようだった。
「…………そんなんじゃ、ねェ」
そういうのでは、ないはずだ。だって彼女は、麦わらの一味なのだから。