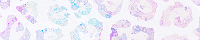 夢じゃなかった
夢じゃなかった
殺風景な部屋だった。白い壁紙に白いシーツとカバーに覆われたベッド、木目調の小さなサイドボード、3人くらいは座れそうなソファに大きめのテレビ、そして扉が一つ。目覚めてすぐ見慣れた光景でないことに気付いた相澤は上体を起こしぐるっと一通り観察してふと視線を落とし息を呑んだ。自分が眠っていたであろうその隣に見慣れたふわふわの耳がある。何事かあったのではないかと顔あたりの布団をめくり様子を窺ったがすやすやと穏やかに眠っているだけのようだった。全部確認できてはいないので断言はできないが怪我などをしているようには見えず、ほっと息を吐き数秒。何故己の生徒、と2人、見知らぬ部屋のベッドで寝ているのか。
「……」
彼女は何か事情を知っているか、とりあえず起こして確認しようと声をかけたのだが起きる気配はなく。余程深い眠りについているのか、気持ちよさそうに寝ているのを起こすのが一瞬躊躇わされたため自身の声が小さくなってしまったのか、あるいはそのどちらもか。いずれにせよ無理に起こすのも気が引け、危険な状態であれば有無を言わさず叩き起こすのだが今のところそうする必要性も感じられず、ここから動く方が危ない可能性もあるので一先ず己だけで調査することにした。
真っ先に扉へ向かった。普通に開いたので警戒しつつ覗き込むとキッチンスペースと奥にさらに扉があり、そちらを開けるとトイレになっている。そしてどれにも窓がなく、扉も2つの部屋同士とトイレへ繋がるものしかなく外へ出ることは不可能だった。冷蔵庫には水、コンロにケトル、横の作業台に缶があり中を開けてみれば茶葉が入っている。飲み物とトイレが用意されているというのは少なくともそれが必要になる時間、滞在することを意味しているのか。そもそもまずこの部屋は何なんだ、恐らく閉じ込められているのだろうが何故自分たちで、その目的意図は。敵からの攻撃なのか。思考を巡らせ最初の部屋に戻りソファの前にあるセンターテーブルに置かれている缶を確認するとお菓子と思われるものが入っていた。それから壁を破壊できないかチェックしてみたが殴る程度ではどうにかなるものではないらしい。こういうとき威力のある個性を持つ者に多少羨ましさを感じる。
「……相澤先生?」
さすがに物音を立てすぎたのか、が身体を起こしてこちらを見ていた。
「起きたか いきなりで悪いがここが何処だかわかるか」
「え?」
部屋を見渡し分からないと首を傾げるに状況を説明すると慌ててベッドから出て駆け寄ってくる。改めて2人で置いてある家具の引き出しなど部屋中を調べ直したが己が見た時と特に変化はなく正直お手上げだ、と思っていたらベッド横のサイドボードを確認していたが「あ!」と声をあげた。
「どうした、何か見つかったか」
「え、えっと……」
何か紙を見つけたらしいはそれを開くと固まり問いかけに答えないのでそばに寄り覗き込むと白いその紙に黒字で一文。
「甘やかさないと出られない部屋……?」
「こっこれは……どういう……」
「……」
ふざけているのか、何の悪戯だと紙を無視して脱出を試みたのだが2人の力ではどうすることもできず立ち尽くす。まさか本当に紙に書いてある通りにしなければ出られないのだろうか。考えたくはないがそういう個性や何かの攻撃を受けているのなら外部からはともかく、こちらからは為す術がないのかもしれない。しばらくの沈黙ののち、顔を見合わせる。試してみるしかないか。言葉にはしなかったがお互いがそう思った。
「では相澤先生……どうぞ!」
どうぞではない。どう考えても逆だろ。相澤は額をおさえた。大の大人が年下、しかも己の生徒に甘えられるわけがないしそんな絵面見たくもない。年齢、関係性などから考えてが甘える側一択である。はあ、と少し大げさにため息を吐き「逆だ」と答えると「エッ!」と立派な尻尾の毛をボワッとさせる。めちゃくちゃ驚いているが本気でこちらを甘やかすつもりだったのか。とは言え、実際どうすれば"甘やかす"に当てはまるのか明確な答えがないので難しい問題である。仕掛けた者の判断によるものなのか、そうすると現在進行形で監視されているのか。カメラらしきものは見当たらなかったが、別の方法で観察されている可能性も当然捨てきれない。とにかくやってみないことには始まらないのでソファへ腰掛けた。
「甘えろ」
「甘えろ……!?」
「そんな~……!?」とあたふたしているを手招きして隣に座らせる。
「相手を俺以外の、身内か何かと思って接しろ」
「そんな無茶な……」
「ずっとこのままでいることになるかもしれん」
「う……、」
お互い何も持ち物がなく、部屋に時計もない。現在の時刻も、ここへ来てどれほど経過したのかも分からないままだ。とにかく指示に従ってみるしかない、と伝えると覚悟を決めたように両手で握りこぶしをつくりふんっと気合を入れる。の、お腹からくう、と音が鳴った。
「……」
「……ごめんなさい、おなかすいちゃいました」
「ああ、……そうだな、」
テーブルの缶にお菓子らしきものが入ってるのは確認したが、それが食べても平気なのかはまだ分からない。いきなりに食べさせるわけにはいかないのでさっと缶を取り中身を1つ取り出し口に入れる。「先生!?」と驚いているに待て、と手で制して咀嚼を続け飲み込んだ。味は普通に美味しいチョコレートで、即効性のある毒などは入っていなさそうである。まあ水分などが用意されているあたりからしても、殺すのが目的ならばあまりにも回りくどすぎるのでその線は薄いだろうと判断しにチョコを差し出した。
「あっありがとうございま、…す?」
「ん」
手で受け取ろうとするからチョコを遠ざけるときょとんと首を傾げるので、もう一度口に近づける。
「せ、先生……」
「口開けろ」
「こっこれは、……あーんですか、」
「早くしろ 溶けるぞ」
意を決して開かれる口に放り込むと、羞恥からか戸惑っていたもほっと表情を緩ませた。まだいるかとの問いに頷くので好きなだけ食わせてやろうとしばらくチョコの包みを開けては手ずから食べさせて、食べるばかりでは喉も乾くだろうと思い飲み物を取りに行こうとするとも立ち上がる。
「淹れてきてやるから待ってろ」
「う……あ、甘えていいんですよね!?」
「ああ……?」
「一人になるのいやなので、ついていきたいです……」
恥ずかしそうに俯き、しかしピンッと垂直に立っている尻尾からみるにかまってほしいと甘えている様子が窺えるので好きにさせることにして隣の部屋へと移動した。ぴったりついてくるに水か茶かを聞くと水が良いというので水切りに置かれていたコップに注ぎ元の部屋へ戻る。部屋の状態に変化はなく、この程度では指示にある甘やかしには届かないということか。再びソファに並んで腰掛け喉を潤ししばしの沈黙のあと。「甘えます!」と声高々に宣言したによしこいと頷くとずいっと一気に身を寄せてきた。
「よ、よしよししてください」
「……おう」
眼前に差し出される頭とふわふわの耳に、そっと手を乗せゆっくり撫でると頬を赤く染め震えていたが徐々にリラックスしたように尻尾が大きくゆっくり揺れ出す。しばらく撫でていると段々身体が下がっていくので大丈夫かと声をかけると「お膝かしてください」と太ももに頭を乗せソファに横たわった。そのまま頭や髪を撫で続けあたりを観察してもまだ変化はない。ふあ、と欠伸をするがこちらに顔を向ける。
「眠いなら寝ていいぞ」
「……せんせいも、」
「俺は良い、」
「甘やかしてくれるって言った、」
身体を起こしてまた寄せられる顔はまだ赤く、羞恥が残っているようだが脱出の為にも"甘える"のを優先しているようだ。胸元に手を添えて「つれてってください、」と言われては断れず後で怒るなよと念を押してその身体を抱えベッドへ連れて行く。ふわふわに添い寝を所望され隣に寝ころぶと懐に擦り寄ってきて身体に尻尾が巻き付いてきた。ぐりぐりと押し付けられる頭を先ほどまでのように撫でると深く呼吸をして、すんすんと嗅がれる。
「オイ、嗅ぐな」
まさか臭うのか、と自分でも嗅ごうとしたら「先生の匂いすきです~」と言われ固まっている間にふわふわは夢の世界へと旅立っていった。
ハッと目が覚め、いつも朝に見る光景と同じものが広がっているのを確認して緊張を解く。夢だったのだろうか。だとしたらとんでもないものを見てしまった。いくら猫好きと言えどもネコ科の個性を持つ教え子とあんな風に接する夢を見るだなんて、極度の猫不足か。猫カフェ行くか……と朝からげっそりしながら準備をしていつも通りに出勤する。
「ヘイ、イレイザー!寝不足か?」
「……はあ」
人の顔見てため息吐くなと騒ぐ声も今なら落ち着くくらいだ。煩悩を消せ仕事に集中しろ、とA組の教室へ向かうとこれまたいつも通りの元気な挨拶に迎えられ内心ほっとしたのも束の間。夢に出てきた生徒、と目が合えば彼女の頬がぽっと赤く染まる。いやまさか。そんなはずはない、と思いたいがは常であればA組生徒の中でも明るく、挨拶も率先して声を出しているのだが今日はもじもじと縮こまっているように見えた。いやまさか。あの部屋での出来事は夢ではなかったのだろうか。