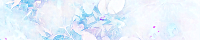 やさしいひと
やさしいひと
例えば、ナミやロビンを呼ぶ時。文字に起こせば語尾にハートがふんだんに付いているのが想像できるくらい、その前に眼や吐き出されるタバコの煙ですらハートになっているくらい彼の女性への態度は分かりやすい。まさに彼自身が口に出して言うメロリンラブ、という感じだ。
「んナミすわぁ~~~ん♡」
「ロビンちゅわん♡ 紅茶をお持ちしました」
例えば、有事の際における優先事項。仲間全員を大切に思っている彼であるがいついかなるときも真っ先に女性陣の心配をする。とても素敵なことだと思う。そういうところが、好きなのだ。
「おれはナミさんを探しに行く!!」
「ロビンちゃんおれが守るからね~!!」
すべてのレディを愛している彼は私にも当然、出会った時から甘くて優しい人だった。なんでもない自分がお姫様になったかのような、そんな気持ちになるくらいとても丁寧に扱ってくれる。女性に対して言動に気を付け、乱暴なことなんて一切しない王子様みたいな人。ひどい扱いを受けていたわけでもないが特別もてはやされたこともない私は息をするように恋に落ちた。でも、違うのだ。ナミやロビンに対するときと私とでは。二人だけではない、降り立った島や敵でも眼をハートにして身体をくねらせメロリンラブと叫ぶ彼の姿はよく見られるが私の前でそうなったことはない。
「ちゃん ココア飲むかい?」
キッチンで作業をしているサンジをぼうっと観察していると声をかけられそれに頷くと差し出されるココアに穏やかな微笑み。大好きなはずの彼の笑顔に胸を締め付けるのは。やっぱり彼にとっての特別が私ではないからだろうか。好きだから、誰よりも幸せになってほしいと思っている。その隣にいるのが誰であろうとこれは本当に、心の底から思っているのだけれど。うそ。だったらどうしてこんなに苦しいの。どこかでそれが私であってほしいと思っている証拠でしょう、私の中にいるなにかがそう訴えてくる。
「甘さの具合はいかがですか?プリンセス」
「サンジのココアはいつだって完璧だよ」
世界で一番おいしい。そう言うと「本当かい?」と目尻を下げた。これを言ったのがナミなら、ロビンなら、サンジはもっとハート乱舞で大喜びするのだろう。私だって二人に褒められたら嬉しくて踊り出すと思う。ナミもロビンもとっても綺麗で優しい、私も大好きな人たちだからそれは当然なことだし二人への態度を改めてほしいなんて思いもしない、むしろ美女にメロリンラブしているのがサンジだと安心さえするのだ。そして自分を卑下するわけじゃないけど二人と自分が違うことも理解しているから良い。
「今日のおやつはスフレチーズケーキだよ」
「アプリコットジャムつき、好きだろ?」といたずらに笑うので私も笑顔で頷く。ナミが好きだと返せばもっと嬉しいだろうな、なんて。二人と自分が違うことを理解しているなんて言いながらいつも勝手に心の中で比べて勝手に傷つく。サンジはレディ相手なら誰にでも優しい。ナミとロビンは誰が見ても美しい。そしてサンジもナミもロビンも私にとても優しくて、大切にしてくれている。間違いなく私を傷つけているのは私自身だ。分かっていても好きな人が綺麗な人にメロリンラブして、自分にはそうではないと感じる度に胸がきゅっとなる。苦しくなることに理由をつけてさらに心を痛めての繰り返し。
「ちゃんはフルーツが好きだもんなァ」
貴方の作る料理を食べるようになってからもっと好きになったよ。苦手だった食べ物も好きになったし、好きだったものはもっと好きになった。なんでも美味しくしてくれる魔法の手。そう褒めると「嬉しいこと言ってくれるね」「クソ幸せモンだおれは」って笑ってくれるけど、私はそれ以上にはなれない。レディに優しいサンジを好きになったくせに、見てくれないならこれ以上優しくしないでなんて思う。自分だけ優しくされなかったら、それでも素敵な彼を好きになって、それはそれで傷つくのに。時折、考える。サンジは私の気持ちに気付いているんじゃないかと。だから、期待させないように過度な反応はしないのではないかと。ナミたちが自分をそういう目で見ていないからこそオープンにメロリンラブしているのでは。彼は自分に興味のない女性相手の方が大胆な気がする。
「特にみかんとぶどうが好きだろ?」
「……うん、一番はぶどうかな」
正解だった。でもみかんと聞くと思い浮かぶ顔がある。好きなものは好きと言えばいい、何も悪いことではない簡単な話なんだけど、なんだか自分の中でみかんはナミ、というイメージが強くて。明るくて爽やか、ハツラツとしていて気が強いところも魅力の美しい人にぴったり。堂々と媚びない姿は見ていて気持ちがいい。そんなナミは「もっと自信持ちなさい!あんた可愛いんだから」とかっこよく笑う。あのナミがそう言ってくれるならとこの船に乗ってから私も少しは自信がついた。でもね、サンジのことに関してだけはダメなんだ。だって分かりやすく違うんだもの。
「ぶどうが一番かァ イイのを見つけたらいっぱい買わねェと」
先のことを考えて楽しそうにあれもいいこれもいいとメニューを並べるサンジは本当に料理が好きなのだろう。少年のような笑顔がかわいい。優しい人。もし私の予想が当たっていて、必要以上に気を持たせないように防衛線を張っているなら構わなければいいのに、こうして私の好きなものを作ってくれようとしている。どこまでもフェミニストな彼に優しくしないなんて選択肢は存在しないのだ。優しさに触れるほどこちらは心奪われる一方だというのに。
「そういや新しい髪留め、もうつけないのかい?」
「え?」
「黄色のやつ こないだ買ったんだろ?」
「あ、うん、買った よく見てるね」
「当然さ それに良く似合ってたから」
ありがとうの言葉は、笑顔は、自然に出せたかな。前の島で、彼の色だと思ってつい買ってしまった髪留めをナミに後押しされすぐに一度だけつけた。男性陣には気付かれないだろうけどなんだかとても気恥ずかしくなってその後つけることなく部屋に眠っている。あの一日のことを、サンジは見ていたのか。どうして、気付いてしまうのだろう。どうして、またひとつ、好きな理由を増やすのだろう。どうして、やめさせてくれないんだろう。良く似合ってただなんて、好きな人の色をつけて、好きな人にそう言われたら誰だって舞い上がってしまう。
「あたたかいちゃんには黄色がよく似合うんだよなァ」
「……そう?じゃあ、またつけよっかな」
「もちろん何色でも素敵だけどね」
「やっぱひだまりの色が特に合ってる」だって。貴方の色だから買ったんだよって言ったらどんな顔をするのかな。困らせてしまうだろうから伝えないけど、サンジが似合うと思ってくれているならこれからもつけよう。彼が私を良いと思ってくれる部分をひとつでも多くしたい。メロリンラブには程遠くても良い。サンジが言ったことを実行する私を見て、少しでも私の存在がサンジの中に残れば、嬉しい。彼に選ばれるのが私以外の誰であっても彼が幸せならば良いだなんていい子ぶっておきながら、自分を見てほしいと思って、動いてしまうのだから恋とは厄介なものだ。