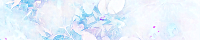 こいごころ
こいごころ
物心ついたときには海上レストラン"バラティエ"にいた。オーナーゼフと古い友人だった父が預けていったのだとか。母は私を産んで間もなく天国へ、父も流行り病にかかり頼れる身内もおらず一人残される赤ん坊の私を信頼できる友人に託したのだ。レストランの経営をしながらただでさえ子供だったサンジがいるのに赤ん坊までとなると、大変だっただろうにオーナーゼフは自身の信念を曲げても私を船において育ててくれたとても優しい人。ゼフと共に私の面倒を見てくれたサンジも、オーナーゼフの"クソコック募集"の文字で集まったチンピラ崩れのコック達も皆優しくしてくれる。私はオーナーゼフはもちろん、バラティエの皆が大好きだった。
「、ここ片付けといてくれ!」
「はい!」
バラティエでの私の仕事は裏方、キッチンや居住スペースなど店内以外の掃除などでお店に出ることは余程でない限りない。店員ではなく家族としてオーナーゼフや皆のお手伝いをさせてもらっていた。だから結局最後までお店のことはよく分からないままだったけど、大好きな人達のそばで過ごせるだけでとても幸せだったからバラティエを出る日が来るなんて思いもせず。
「ちゃん今日のおやつはケーキだぜ」
「休憩の時に食べな」と微笑むサンジは誰よりも優しい。いつも私のためにデザートを用意してくれたり重い物を持ってくれたり、コック同士の喧嘩に巻き込まれないように守ってくれたり。皆優しいけどサンジは特によく気にかけてくれていた。年も近く、いつもそばにいて優しくしてくれる王子様のようにかっこよくて素敵なサンジに恋をするのは当然のことだと思う。サンジが女性客相手にメロリン状態になり、オーナー達に鼻の下を伸ばすなと怒られていても、私にはそうならなくても、でもずうっと甘くて大切にされている自覚があるのでそれで良かった。バラティエの皆が、オーナーが、自分が、サンジの特別である自信があったのだ。
「お前はいいコックだから一緒に海賊やろう!!」
麦わら帽子が良く似合う彼が来た時、何かが変わる予感がした。"女の勘"というものかもしれない。その勘のようなものは実際当たっていて、クリークの襲撃や色んなことが起こり様々な思いが交錯し騒動を終えて、サンジはバラティエを出て麦わら帽子の海賊ルフィと共に海へ出ることになる。そして私も、家事くらいしかできることのない私も、オーナーゼフに背中を押されルフィが頷いてくれたおかげで、一番好きな人と離れることなく麦わらの一味として船に乗せてもらえることになった。
「ちゃんはおれが守るから」
サンジはそう言ってくれたし、ルフィもゾロも、ナミやウソップも優しくて私はすぐに皆を好きになり、皆のためにできることをしようと自分の役割を探して。少しでも足手纏いにならないように特訓したりウソップに私でも扱える武器を作ってもらったり。そうしてこの船でたくさんの冒険をしていく中で気付いた。私は彼の特別であったとしても、私の望むものではなかったのだと。
「んナミさ~~~ん♡ 今日も素敵だ~♡」
メロリンラブしているサンジは見慣れている。お店に来た綺麗な女性達にもいつもこうだったから。ナミだけでなく、ロビンというまた違うタイプの美しい人が増えて、アラバスタでお別れしてしまったけどビビという王女もとても素敵な人で。サンジは眼をハートにしてメロメロになっていた。いつものことだと、これがサンジだと思っていたから、そうはならないけど一番私を甘やかして、大切にしてくれているから彼の隣にいるのは自分なのだと安心していたのだけれど。だっていつだって気にかけてくれて、好きなものを覚えていてくれて、海に出てからは降り立った島で見知らぬ人に良くない絡まれ方をしたときなんか飛んできて「ちゃんに何してやがる!」とあっという間に追い払ってくれて。もちろん私だけじゃなくナミ達のこともそうやって守っている。それでも私は、私が最もサンジに近いと思っていた。
「は素直で良い子だよなあ」
私のことをそう褒めてくれたウソップの言葉にサンジが答えるのを聞くまでは。
「ちゃんクソかわいいだろ」
「何でサンジがドヤ顔してんだよ!……やっぱ好きなのか?」
「そりゃァ好きに決まってる
かわいい妹だ」
愛してるに決まってる。好き、愛してる、そこだけならどれほど良かったことか。でも思ったよりもショックはなかった。自分が特別であると自覚していたその立ち位置というものを、本当はちゃんと分かっていたのだと理解させられたようだ。ああ、やっぱりそうだよね。そういう納得の方が大きい。自分が思っていたものと違っていても、大好きな人に愛していると言ってもらえるのは嬉しい。
「ガキの頃から一緒にいたっつってたもんなあ」
「ああ ちゃんがこーんな小せェときから」
「昔っから天使さ」と口角を上げるサンジの眼には慈愛に満ちていて。この人は本当に私のことを想ってくれているとすぐに分かる。こーんな小せェときから、と親指と人差し指でサイズを例える彼にそんなに小さくはないと笑みが零れ、大丈夫だ私は笑えていると安心した。ツッコミをいれてやろうと二人に近付く。
「そんなに小さくないよ~」
「聞いてたのかい? おれにとっちゃそれくらい小さくて可愛い天使だったんだぜ」
「サンジが兄貴じゃも苦労するなァ」
じくじく。胸の奥の痛みも、平気だ。私はいつもの笑顔で冗談を返せているから。
「ちゃん レモネードをどうぞ」
「ありがとう!」
サンジが作ってくれるレモネードが好きだ。爽やかで甘い。まるで作り主のよう。
「いつものレモネード 皆のこと思い出すなあ」
バラティエの皆は元気にしているだろうか、そう続けると「あいつらなら病気の方が逃げ出すさ」といたずらな笑顔で言うので私も声を出して笑った。オーナーや皆も恋しいけど、麦わらの皆と離れるのもイヤだし出会えて、一緒に冒険をさせてもらえて、大変なことももちろんあるけど本当に楽しくて毎日が幸せだ。サンジがいてくれるから尚のこと。バラティエでサンジの帰りをただ待っていただけなら気付けなかったこともある。
「寂しい?」
「そりゃあ寂しくないって言ったらうそになるけど」
「はは、そうだね」
「サンジとルフィ達がいるから幸せ」
「そりゃあよかった」
目尻を下げるサンジに、高鳴るこの胸もいずれ感じなくなるのかな。いつかサンジが私を想うように、私もサンジを本当の兄のような、家族として愛する気持ちに落ち着くのかな。その日まで、まだこの恋を大切にしていてもいいですか。